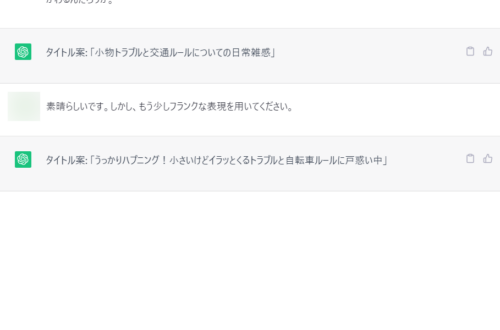-
「津軽のカマリ」を観た
高橋竹山である。
その名は数多の音楽愛好家に広く轟き、津軽三味線と言えばまず名前の挙がる人物とされている。自分は伝統音楽に明るくはないのでして、その名を知ったのはJINMOというアーティストのギターマガジン連載コラムか何かだった。当時ギターを愛好していた自分にもずいぶんと感じ入るものがあったと記憶している。氏は眼前で初代高橋竹山の生演奏を観たことがある、とか書いてあった気がする。
というような事を調べていたら、2002年当時の連載記事がjinmo氏のサイトで読める。個人的には映像よりもこっちを発見したことのほうが驚きだった。読みふけってしまった。
http://www.jinmo.com/00/en/other/words/words11.html
上記リンク先のJINMO氏の文章が当事者視点も含めて大変に読みごたえがあり、高橋竹山という人物について自分が何か言える事はない。
さて映像本編。映像は冒頭から雪に埋もれる景色。高橋竹山の演奏映像集といった趣ではなく、彼の人生、取り巻く人々についてもふんだんに盛り込まれ、門弟などゆかりのある人々が出演しており大変に良い雰囲気だ。それでも演奏場面も多く散りばめられていて大変に満足。二代目高橋竹山のロードムービー的な趣もある。二代目は茶道の先生みたいな品のある姉さんだ。ひたすらに演奏を楽しみたい人には本作は不満かもしれないが、それは音源をお買い求めれば良いの話。
肝心の演奏については、どうもしっくりこないというか、ピンとこないというか。中途半端にギターに馴染んだ時期もあるだけに、比較してしまうのかなあ。まさか高橋竹山と自分の演奏を比較するなんて話ではなくて、三味線の音の特性って言ったらいいんだろうか。リバーブの少ない単音メインの演奏はどこか迫力に乏しく思えてしまう。あるいはこの作品の音声による印象なのか。素人なので深い話もできないが、とにかく本作の演奏自体には満足できなかったのがちょっと残念。
何かに混じってると音色がすごく生きてるような印象あるんだよなあ。
-
「ドン・キホーテ」を読んだ
まんがで読破シリーズがもうちょっとだけ続くんじゃ。
原書は未読、しかしなんとなくあらすじは知っているという状態で拝読。調べてみてビックリしてしまったんだけど、原書はなんでも世界最高の文学作品の一つだとか、世界で最も売れた書籍だとか言われているらしい。マ?しかしながら、以下はあくまでもこのまんが版を読んだうえでの感想文。
まず、少年ジャンプとかにそのまま載ってそうな冒険漫画でした。しかしながら主人公は地主の老人で、身分のある人が暇を持て余し、メンタルブチ切れで旅に出るって話。その旅路は割と狭い範囲だったんだろうか、奇行の噂話は彼を心配して旅立つ前に引き止めた人々に知れ渡っていく。そうして一同は彼を連れ戻すべく画策するんだけども…。原作読んでないので分からないですけど、まんが版ではこの騒動のあたりがだいぶ端折られているような印象を受けました。
作中にも出てくる「このバカ騒ぎを真似た第二第三のドン・キホーテが出てくる前に止めねば」という意見はなんとも心当たりのある話じゃないかしら。現代では、ある種の人を「ドン・キホーテ」と例えて言うのが広まっている印象がある。どんな種類の人かっていうとそこが、ま、難しい気がするんですけど。姿かたち立ち振る舞いだけ真似して自らもカリスマならんという人とかあ?もう少し本作の内容をかみ砕けば、誇張であるとか不能であるという認識が本当はあるのにカリスマ仕草に溺れてしまって客観的には無鉄砲とかtrollかって人。埋蔵金とかUFOとかの界隈が近しいか。どっちも本当にあったというどんでん返しの可能性がゼロではないあたりも含めて、当人がシリアスなればなお一層滑稽に見えてしまう。電波系とか迷惑系とか。
ところがドン・キホーテ”本人”はそんな電波系とか迷惑系とは違っていたことが最後に明かされるわけでして…。
本作を読んでいるうち、風船おじさんの騒動を思い出した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E5%98%89%E5%92%8C
世の道理に耳を貸さない無茶が、世に風穴を開けるみたいな発想、あまり好かない。そりゃあ無理難題に挑むのが人生ってものかもしれないが、まずはあくまでも冷静に、計算高くやることをヨシとしなければ。常識人の振る舞いじゃないと。少なくともドン・キホーテには騎士としての誇りと良識があったのだろう。ところがそれ自体が世の中とずれていた。世の中は変わってしまうものなのだ。しかしドン・キホーテが、変わった世の中で見つけた幸福というものは…やっぱり少年ジャンプとかにそのまま載ってそうです。
つまりやめとけってこと。
-
青空文庫の引っ越し
いつの事だったか、青空文庫が新しい環境への引っ越し検討していると目にした。日本のインターネットを代表するレベルの大御所webサイトだと思う。いよいよ新しい環境での運用が始まりそうだ。とはいえ、部外者には細かなところは全くわからない。今だって年一の挨拶で更新される「そらもよう」以外に情報はない。遡ると2022年の年頭までには計画が始まっていたようだ。
新しい環境のミラーサイトもしばらく前から公開されている。表立って大きく機能が増えたりということは…ないのかな?
https://www.aozora-renewal.cloud
このwebサイトが提供する価値は確固たるものがあると思う。だから活動の軸がぶれないのだろう。機能を増やしてみるなどという事も、もはや必要ないのかしら。例えば物凄い高パフォーマンスをたたき出すサーバである必要もない気がするので、新しい試みのためというよりは、次の数十年このサービスを存続させることを見据えてのお引越しなのかもしれない。
ここのところ、読んでみたい書籍が意外と電子書籍になってないものだと気付いた。「風の谷のナウシカ」の原作っていうのかな?漫画版のやつとか、宮部みゆきの「模倣犯」や、「ユリシーズ」など。そりゃあ当然、誰かが電子書籍化の作業をしてインターネット上で販売、あるいは公開せねばならない。既に紙書籍で販売されているとなると、電子書籍化以前に、ビジネスや著作権法上の問題がクリアできてないとその作業に手を付ける事もできないのだろう。…たぶん。公開してないだけで下準備ぐらいはされてたりしねえのだろうか。
(ここで、電子書籍化って具体的に何をするものなのか、技術的な面を何も知らんもんだなあと思い当たる)
青空文庫で取り扱うものは話が少し別で、平易に言えば著作権が切れた作家(作品)が対象になる。公開形式もhtmlやテキストファイルであって、作るのにも読むのにもそこまで特別な環境は要らない。作成者はボランティアの皆様。青空文庫のこの方針は、おそらくは今回のリニューアル後も変わらないのではないか。
このまま何十年か経過したら、どうなっているんだろうと想像した。例えば、電子書籍としてしか販売・公開されていないような書籍はどうなるんだろう。今でも現存すると思う。Amazonにも個人で描いた漫画みたいなものは山ほどある。無料の物だってある。文学というジャンルだってあるだろう。青空文庫での扱いはどうなるんだろうか。今まで同様、ボランティアの手によりwebブラウザで閲覧可能な形に変換して公開するのだろうか?そうだとしてもいったい、何年先の話なんだろう。
そもそもが、著作権が切れたものを残すという主旨の筈なので、原典が紙だろうと石板だろうと電子書籍だろうと、権利が残っているものは青空文庫に載らない。明示的に自由に使えるという許諾があるものは別のようだ。そして、広い意味での電子データになってない書物を残すこと、デジタルアーカイブ化に本質的なサービスの存在意義があるというのなら、最初から電子書籍だったものは対象外だったりするんだろうか。うーん。
ま。
仮に、今後の電子はシラネってスタンスでも、青空文庫は現時点で十分に大きな役割を果たしていると思われます。今後の引っ越しでどうなるか。何も変わらんなあ、でも十分にアゲ👆
-
まあ雑記
有名な宮沢賢治の「雨ニモマケズ…」を青空文庫で読んだ。最後にお経のようなものが並んでいて驚いた。俺は初めて読んだんだろうか。もはや覚えていない。冒頭と、玄米四合のあたりだけ記憶にあった。…そもそもなんでこれ有名なんだっけ?
https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/card45630.html
という文章にインスパイアされたわけでもないけど、本当に一日に玄米を4合食った。朝に2合炊き1合杭食い、昼に1合食い、夜に2合炊き全食いうおおおお。大満腹でありますね。納豆と焼き魚、鯛の刺身とか、さらには牛タンやら酢の物、筑前煮、大豪勢。また、玄米に味噌を乗せて柚子七味唐辛子をまぶして食ってみたりもする。うーん。うめえ。今後も玄米で良いのかもしれないな。炊飯器で普通に炊けるし、水加減を少なめにしても好みの感じに炊ける。今さっき書いたとおり、メシが好きすぎてとんでもない量を食ったりするので、日常的には炊かないようにしているという状態も踏まえたうえで、白米より良いんじゃねえの。うどんより蕎麦ぐらいの感じで。
ついでに青空文庫の話を連打、「ルバイヤート」があったので読んでみた。しかし特に面白いものでもなく、ざーっと流し読みして終わってしまった。その名前は世界史の授業で習ったんじゃなかったかと記憶しているが、なんでこれがそんなに有名なのか、イミフだったので調べてみる。よーするに、「酒のめうぇーい」みたいなこと言ってるのがウケたらしい。書かれたのは十字軍とバチバチやってるころのペルシアだけど、西洋では19世にこの作品が発見されて人気になったと。「昔の人はこんな事いってた!流石だ!」みたいな感じだろうか。例えば今の日本で徒然草とか土佐日記がウケるようなもんか?🤔あるいはそんな呑気なものではなくて、当時の世相というかそういうものにマッチしたと…AI君しらべではこの本が発見されたころ、「共産党宣言」とか「種の起源」あたりが西欧では話題になって、当時の価値観にゆすぶりをかけていたと。いわゆる教会と聖書みたいな価値観?本書はゆすぶりの追い打ちみたいなもんだったのか。太古の詩でそんな揺らぐもんかね、って思ったけど、聖書だって太古の書みたいなもんで、それでやってきた価値観だから、置き換えて考えてみるのも当時の人には受け入れやすかったのかもしれない。妄の想でやんすが。
https://www.aozora.gr.jp/cards/000288/files/1760_23850.html
新たな収納を導入した。旧収納から移動させる時こそが合理的な断捨離の好機なんだけど、どれだけ収まるか検証も大事なんではと思い、ドゴシャと全量詰め込む。目論見通りに収まり、結果として旧収納の設置場所、80x80x天井までぐらいの有効スペースを増やすことが可能になりそうだ。しかし有効活用の予定はない。だから、何か新しいものを手に入れて置いてみるかという考えもあるけど、これ以上物を増やしてどないすんねん。もし部屋にある全てをうまく再配置してみれば、今より良い感じになるかもしれない。
👆…というその再配置もやってみた。住居空間の占有効率は良くなったが、収納内の効率が落ちたような感じ。生活導線の改善はできたからええか。賃貸一人住まいで導線ていうのも大袈裟な感じあるけど、確かに今までより効率的に外出の準備とか着替えとかできるようになったった。QOLとかいうの、これのことかね。
投票日が雪の予報ということで、期日前投票。同じ事を考えている人多数と見えて、案外賑わっていた…ような?期日前なんて滅多にやらないしわからん。寒々しい会場で対応してくださった皆様お疲れさまでした。あれって市役所職員なのかね?
-
踝にはためく風の冷たきこと
関太よりは細い、しかしどうみても肥満、という身体的特徴なので諸々あります。パンツ(ズボン)の股が擦り切れるというのはあるあるで、こすれて薄くなり、やがては穴が開いてしまう。股下が広い?大きい?ものだったらそういう事も少ないのですが、わりとフィットしているものだと避けられない。いや痩せろ。
素材や利用頻度にもよるんでしょうけど、6年ぐらい履いたデニムにとうとう穴が開いた。もちろん予兆はあったので、ついでとばかりに何本か新しいパンツをお買い上げしておいたのだが、ネットで買ったため、裾がながーーい。ものぐさなので放っておいたものの、穴が開いてはこいつらを稼働させねば致し方なし。今回もアイロンで圧着する裾上げテープで対応しようと思っていた。以前試したときはうまくいった。
といった頃合い、洋服のお直しをやっている店があった。持ち込んでお丈の調整を願いしてみることにした。後日、無事に受け取り。勿論何の問題も無い。頼んでよかった。今では家庭にミシンなんて無いことが多いと思うけど、昔のカーチャンはこういうの自宅でやってたんだろうか。
粗大ごみ出荷待ちをしている椅子が部屋の中に置いてある。邪魔なのだけど、取り込んだ洗濯物とか薬局で買ってきたものとかをまずはドカッと置く場所として重宝している。世の人はソファでこれをやるらしい。ソファとは洗濯物置き場だとすらも。ソファのある暮らしをした事ないなあ。今後する予定も…見当たらない。広いおうち、ただくつろぐだけの部屋…。しょんぼり(´・ω・`)
I’m sofa king live alone.
夜明け前の非常に寒い薄暗い時間帯、神社に人影、らしきもの、があってギョッとする。神殿の前でじっと立ち尽くしている。たぶん手を合わせて願掛けしているのだろう。個人の願い事なんてすぐ済む。なんなら敷地に入らず、横目に通り過ぎる間に済んでしまうようなもんだろ、お金が欲しいとか無病息災とか。そんなもんでいいよ。しかし、あの人影の様子は自分のための祈りではないんだろうなと想像してしまった。なんの事情か知らんけど、こんな時刻、そんな様子、どうしてもお願いをする必要がなにかしらあるんだろう。目は開けているだろうか。物言わぬ社に、少しでも祈りの届いた印でも顕れないかと暗がりを凝視している、そんな風に思えた。俺の足音は耳に入っているかもしれない。邪魔してしまったか、菩薩到来を誤認させてしまったやもしれん。あなや、セキフトシヨリハホソイノミコト、貴下の祈りを聞き入れるに能わず、丈が合わぬゆえ。
七草粥を食べた事ないのは、まずお粥が好きじゃないからで、たぶん七草自体は食べられないということは無い筈。って調べたら、セリ以外の食材になんの心当たりもねえわ!すずなとすずしろがカブとダイコンの事らしいのでそいつらは良いとして、残りは何処で出会えるんだろうか。七草粥セットみたいにして売られているのは存じ上げてますけど、単体で売られたりするのだろうか?
二月。