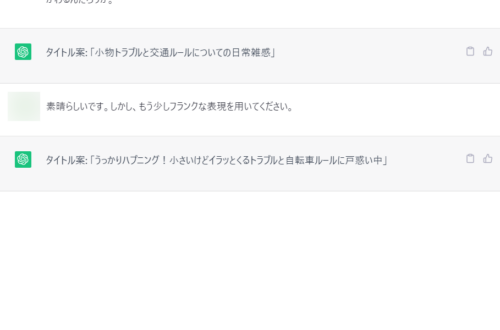ふでのゆくまま
-
春風の諭吉さんを地下に辱め濡らすこと
春は名のみの、風の寒さや雨の酷さやうへ傘壊れたあばばばたたたたタクシー!
コートは要るまいと休日出勤、一駅歩く余裕など見せながら登場、しかし担当業務はわりとあばばばば、まあ時間通りに終わりまして、今度は自社業務に移動しなくては、というところで外に出ると嵐だった。時間に余裕があるし、天気も良いし、なんて思ってたんだけど、まあタクシー拾って移動するよねこれは。自社での書類作成的な仕事を終えると、雨は止んでいた。書店で読み始めた漫画を買う。
闇金ウシジマ君というタイトルは何かで知ってたんだけど、読んだことなかったので、つい、と古本屋で1-3巻まで買ったのだけどまあこれが面白い。先日買ったバスタードの27巻が今年度ワーストの買い物候補筆頭になるほどアレだったのに比べるとなんと素晴らしいことでしょうか。出勤前、出勤後、帰宅前、あらゆる場所で買い足して手元には8巻までありますが、残り全部買ってこようそうしよう。
という、出費の予定でハタと手が止まる
びんぼう常識人。まな板欲しい、ジップロック買うか、麦茶用ピッチャーって100円ショップにあるかしら、あああ。迷う閾値が安すぎる、そんな俺にはやっぱし、闇金ウシジマ君はリアリティあって面白い。タクシーから降りるときに財布を落としてしまい、諭吉さん(ソロ)が雨水に濡れた。数年前にこの辺で財布を落とした。そのへんうろついてるホームレスががめたんだろう。だったらこちらの顔はばれている。何か手がかりでも掴めないかと道行くホームレスにガンとばしていたのがもはや懐かしい。会社の近所に定住しているあいつだったりしねえかな。このまま雨に流されてしまへ。
去年のこの時期は被災した実家に帰る算段をつけていたところで、高速バスが復旧したとか聞いて空いてる便がないか大慌てで探したもんだった。幸いスカスカでちょっとコケた。今年は落ち着いて春を受け入れたいが、このブログを書いてて野菜スープがちょっと焦げた。ダメだこりゃ。
-
細々とした変化をこなすと、ついでにこれもやっておくか、となる。
先日も弊社のガテン部のお仕事を手伝う予定があり、久々に装備などを出してみるもバッグがカビ臭いとかそんなので洗濯機に放り込んでゴンゴンゴンゴン。20年前から俺の物であるこのショルダーバッグ、いまではこうして装備入れとして年に1,2回の出番を待っている。にしてもそろそろな・・・。
で。そうしてバッグを洗いの乾かしの装備を整えの、とやっていると押入れを開けたついでだええええええい、とごそごそ引っ張り出して捨てたりまとめたり入れ替えたり
が
終わらなくてガラクタの中に眠ること二晩。もう4日ほど添い寝の儀。まいどまいど、テキトー過ぎるわけです。
流石に枕元の箱を開けたら革靴が出てきた時はしょんぼりしました。避難用のジョギングシューズが押入れから出てきました。死にたい、っていうか死ぬ。
-
BASTARD!! 27巻 発売!
あまりに驚いてブログ書いた。バスタードの新刊が出るらしい。ほえー。
ここ数年、MMOの開発中止だったり、同人の宣伝に本体商品のページ割くなよwとか、まるで良い話題のない作品となってしまっていた。作者は結婚したらしいけど。ストーリーも破綻とまではいかないけど、なんかこう・・・ねえ・・・。この27巻も延期という扱いのまま過ぎること数年?ここにきてようやく発売の一報が!!気づかなかったわー。26巻以前は捨ててしまって話の繋がりが良く分からない。だから何となくの惰性で読むんだけど、ここまでくると看取りたい、みたいな感情がわいてきます。あー、これを愛着というのですか。
ダッドリー使うときも心はコンロン、そんなピザジェッパでありたいです。ヨウヘイスペシャルで10割!
-
天気予報・・・において、一番の感心ごとは降水確率でありましょう。一般的にはね。この季節だとなふん 花粉症で花粉予想が気になる人も多いだろうし、夏の紫外線情報が気になる人だって多いかもね。ただ、あんなの予報しなくたって春に花粉が来て夏に紫外線が強いなんてわかってるもんだ。だから、花粉症対策、紫外線対策、諸々すればよろしい。
そこんとこ降水確率となると、なると、あれ・・・傘持ってれば同じじゃねえの。時々雨が降る、なんてことはわかってるもんだ。
とも思ったんだが、やはり雨の降るタイミングというのはあまりにも生活に密着している。個人の肩を濡らさないだけなら傘を持てば良いのだけれど、まあ例えば運動会とかハイキングとか。大きな荷物を運ぶだとか。漁に出るだの。もちろんお洗濯。そゆの。まさに天の気持ち。ある時間は晴れる、ある時間は止む、その予報が的確ならば、情報の価値はあがる。登山ならまだしも、雲が出たから引越し中止、などと言っていたのでは現代ライフは濁って腐るんだ。にしても、雨でも平気というシチュエーションは多いだろう。ふと思った。我々は雨の何をそんなに気にしているのか。おべべが濡れることはそんなにも一大事か?
一大事だ。分かっている被害を避けることが出来ないという意味で、一大事。
雨の日に混んでる電車に乗っていると、他人の傘で服が濡れる。そんなものもう、気にしないよね。とはいえそんな無頓着ではいられないから、普通の人は、傘はたたんで持ち込むし、濡れたカバンはタオルやハンカチで雫を拭うぐらいする。みんな塗れてますものね、ほほほ。えっ、あなた傘もタオルも持たずにそんな。あ、ちょっと近づかないで、あっ、あっ、てめ、どっかいけクソが。
雨に歌えば、誹りを受ける。水に流すことも難しい世の中で御座います由。
というわけで、傘を買い換えた。評判の高い傘をサービスポイント的なあれで無料ゲットしたのだが、一年もたつと開いた状態を保持しにくくなってしまった。さして歩いていると突然に、ぱふ、と突っ張りが聞かなくなって、閉じてしまう。ゲゲゲの鬼太郎にこんなのいなかったな、一本足の。あるいはKKK的な衣装。袋を被ったようになってしまう。先日は信号待ちをしている間にそんな状態になり、慌てて直してみると、開けた視界の先で小学生が爆笑しておったぐぬぬぬぬぬぬぬぬ。
傘なんて、一発ヒットすれば世界的な需要があるだろうに、なんかこう、本気で技術をつぎ込んだような気配がない気がするよね?何も浮かべとか言わないからさ、たたみ易くて、軽くて、丈夫なもの、もうワンステップ進化しないかなあと思いますだに。
ちなみにダメになってしまったのはこれ。評判もいいんだけどね。
-
ウェットティッシュで机の上を拭いた。途端に異臭が漂う。ヤバそうな匂いに、思わず窓際にすっ飛んでって開け放つ。すうはあすうはあ。どうやらアルコール入りの除菌タイプを買ってしまったらしい。除菌は良いのだけどこれは強烈過ぎませんか。菌と一緒に人間が死ぬ。
春の訪れ、虫さんたちも登場するので、まあ水回りの衛生には気を遣いたいですが、この殺戮ティッシュ、水回りで役に立つとも思えず、遺憾ながら燃えるゴミへのフリーエージェントが見込まれる三月、イチローは今年はどうかなあ。