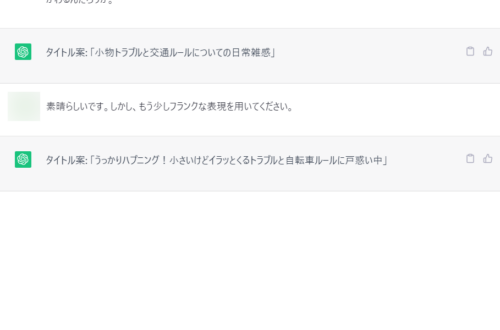-
JUMP
子どものころに平成を迎えたという世代の思い出話。
Amazonプライムで、「魁!!男塾」の第一巻が無料になっていたので読んでみた。何度か読んだことがあるものの、やはり「その後の作風と比べてだいぶ趣が異なるなあ」という印象になる。「学園ギャグ路線」とでも言えばいいんだろうか。無茶苦茶な学校で無茶苦茶な事をしている、という、どちらかというと滑稽話が多い。周辺住民や警官なども登場したり、生徒が街へ繰り出した場面もあったりして、社会の一員としての学校であるという体裁を保っている。
その後、話の細かいところは覚えていないのだが、学園内部での決闘だとか学園を代表して
奇人演芸会武闘イベントに出場するという話が延々繰り返されて終結する…と記憶している。バトルばっかりしていた。当時週刊少年ジャンプに連載していた他の作品も、同じようにバトルばっかりになったと記憶してる。覚えている当時読んでいた作品を並べてみるか。ほれ同世代もがんがれ。
「ドラゴンボール」はそういう方向性でおなじみ。バトルの方向性は、本作の人気が嚆矢だったんじゃねえのか?「ジャングルの王者ターちゃん」までいつしか殴る蹴るの場面ばっかりだったように思う。「燃えるお兄さん」もかめはめ波みないなの放ってなかった?「幽遊白書」もどういう流れで妖怪だか魔物だかとしばきあう話になったんだっけ…??「るろうに剣心」は剣客の時代劇というテイだから斬り合いぐらいするのが自然か。「スラムダンク」もスポーツなんだから強敵と勝負するのは普通のことだな。「聖闘士星矢」も闘士っていうぐらいだもんね…これジャンプだっけ?ジャンプ以外に読んでなかったから、読んだ記憶があるということは、連載していたはずだけど。「シティハンター」は裏社会ものだから命を削るやりとりも納得か。銃を撃ってるし。「こち亀」はどうだったかな。少なくとも両津と大原のバトル漫画ではなかった。あとは…なんか野球の漫画があった気がする。あれ?「BASTARD!!」もジャンプじゃなかったっけ?少年にはエッチな場面がまあなんだ…その。
思い出せるのはこんなもんかな。で、正解探しに当時の連載作リストをネットで調べたら、なんと「北斗の拳」が漏れている。ひでぶ。「ついでにとんちんかん」も大好きだったのに思い出せなかった。「ハイスクール奇面組」もジャンプだっけ…?ジャンプしか買ってなかったのは確かだが、当時は友達の家に行くと兄弟が読んでいる漫画とかがあって、読ませてもらったりもしてたもんだし。床屋の待ち席にも山ほど漫画置いてあった。とにかく。
そう自分は、週刊少年ジャンプとファミコンで子供時代をすごした。世の多くの人と同じく。お父さんお母さんありがとう。
で。週刊少年ジャンプには「友情努力勝利」というキャッチコピーがあったと記憶してる。バトルが人気でたからこんなことを言い出したのか、当初からこういう方向性だったのがいくつかのヒット作で実を結んだのか。この疑問の答えもネットに求めると、驚いた。まず、このコピーは公式に謳われたものではなかった。しかしその方向性は1960年代から見受けられるというのだ。単なる集英社の(あるいは週刊少年ジャンプを担当していた部分の)社風?習慣?ということだろうか。何となくでこんな端的な単語三つにならんと思うので、社内に貼ってあったりしたんじゃないかと想像する。
キッズの自分がそんなキャッチコピーを当時から意識していたとは…思えない。でも、おっさんの自分が週刊少年ジャンプを思い出すにあたり、セットで出てくるフレーズということは、当時読んだ作品の印象に、違和感なくマッチするものなんだろう。例えば…「死ねいっ」「ぐはっ!」とかやりあってたのが、同じチームになって仲間となり、新たな敵と戦うとか。仲間を思う気持ちで強大な力に目覚めるとか。
このパターンが、物語の王道パターンと感じる。これは…週刊少年ジャンプで育ったから?それとも、世の中の道理というか人間の歴史を経た感情として世界共通の当然の何かだとか?美しい人生のテンプレ。俺の友情、俺の努力、俺の勝利!!脳筋か。
大人になったからには悪ふざけだ、逆の方向性をキャッチコピーにしよう。例えば「冷淡怠慢逃亡」はどんな感じになるだろう。関わらない耐え忍ばない戦わないの3ない運動。美しい人生のテンプレ。逃げるが勝ちならJUMPで勝ち確だって?いやあさすがに嘘だ。愛をとりもろせ。あべし。
-
めし短観2023年1月
大晦日には特に工夫もなく、カップヌードルのフォーを頂きました。日本でいまどき細く長く生きたい奴なんていねーよ。そんな尖ったことを言ってみたいものですが、年明け早々北朝鮮からミサイルが届き、細く長い平和な暮らしの有難みが染みる。につぽんの そばにいるのは こんなやーつ。れーわ5年も地球はハードコアになりそうです。人生。
正月は例年通り、酒を頂く。きっちり一年ぶりではないかと思う。スミノフアイスを一本。300ml。酔う。それ以上飲む気になれず。これも例年通りか。年末、値上がりする前に買っておいたカマボコをまるかじり。練りに練った人生…めんどくさいだけかな。
ハナマサのカレーうまいんだが、サイズが特大で困る。ああいうのは一食を手軽に済ますのが便利だと思うのだが。家族であれを食うなんてことあるんだろうか。家族でレトルトカレーにしよう!ってなったらバリエーション揃えたくない?だから、家族食いはあまりなさそうだと考えると…そこらの喫茶店とかでつかうのに便利なのかね?備蓄とか?そして同じくハナマサの搾菜がくそまずでびっくり。他の搾菜は桃屋の瓶詰のあれぐらいしか食ったことないが全然別物だ。なんというか、塩気が薄い?水っぽい?こっちのほうが現地の人には合ったりするんだろうか。
カクヤスで買った高級ポテチがうまい。高級いうても500円ぐらい?だったと思いますが。日本製品と違って中身が袋いっぱい詰まってるのが良い。聞いてるかカルビーと湖池屋。
https://www.kakuyasu.co.jp/store/commodity/0010/00351239/?bid=gcaat_00351239
日清の「シビ辛 麻辣大豆ミート」なるものを食う。大豆ミート関連商品はほんと美味しくなったと何度もいってますがあ。たぶん、その分油っぽくなったような気がするが実際どうだろうか。本品もうまい。美味いので瓶からそのままモリモリ食ったら消失した。怪異である。食べたら無くなる人生。
http://nissin.com/jp/products/items/11483
お魚の種類の英語表現の語彙を増やしたい、と思って何個か調べて忘れて…いくつかは覚えた。料理動画なんかでは「すなっぱー」と「いえろーている」が良く出てくる。タイとブリ。で、ハマチもyellow tailのようだ。ま、出世魚ということで、同じでも問題ないでしょう。ホッケを「sea bass」とか「sea bass fish」と呼ばれると覚えていたのたが、これが誤りで、スズキがsea bassのようだ。ホッケは「Atka mackerel」だそうな。え、mackerel?ってことは、サバの仲間なのか。調べてみようと思ったが、ネットではあまりその辺に言及された情報はなかった。お約束のwikipediaで調べてみても、分類もまったく違う。「サバに似たやつ」みたいな通称が定着したんだろか。見た目には似てないが…。似たやつ呼ばわりの人生。
ウナギの完全養殖ができそうな…もうちょっとかかりそうな…そんな状況らしい。いや、もともと養殖ものあるじゃん?って思たけど、よくわかんないがウナギの養殖というのは「稚魚を獲ってきて食えるサイズまで育てている」という状態らしい。そうすると全部オスに育つらしい。えええええ!?!?で、それが、卵から孵化させて食えるサイズに育てることができるようになるとか。ウナギ大好きなんだよねえ。はよ実現しないか。できれば今年中に。そしたら大みそかにウナギを食う。
除夜の鐘に先駆けて街を覆う蒲焼の香り。北風に背を丸めて歩む人がうの字に見えた。
-
湯水に替えて
スマホ便利だ。時計がついている。目覚まし時計にタイマー、ストップウォッチまでついているのが実に便利で、助かる。…いや、ストップウォッチはさすがに出番がない。
ある夜のことで御座います。
風呂に湯を張らんとお湯を出しました。カランからドバドバとバスタブに。ふいに、タイマーをセットしようと思い立つ。普段はこんなことをしません。うっかりしても、水とガスが無駄になるものの燃えたの壊れたのという話にはならんので気を抜いています。じっさいうっかりしたことは何度か御座います。とんでもないことをしてしまった!と愕然とした素振りを見せ、しかし居直っていやっほうとお湯を溢れさせて湯につかりまザザザザ。
このカランというのは、何を意味しているんだろうか。故郷の家もたしかにこうだった。カランと書いてあった。よそのお宅の風呂を使う機会はないが、以前に一度、旅先で世話になったお宅でもそうだ、カランだ。ある古い動画でも使われていた、というブログを見つけ、いよいよ気になってネットで調べる。自分の読みでは、仏教関連の古い言葉を漢字ではなくカタカナ表記したようなものではないかと思った。
すると、オランダ語「kraan」を語源とするようだ。鶴の意味。鶴の首みたいに見えるということのようでなるほどなっとく。んじゃ英語圏ではクレーンというのだろうか?こちらも調べると、「faucet」という。しかしこれはアメリカで主に使われる表現であり、イギリスでは「tap」という。前者は聞き覚えが無く、後者は他にも意味がある単語で、その由来を想像だにしない。画像検索してみると、両社とも確かに「カラン」の画像が出てくる。でもどっちかというと、tapの検索結果のが小ぶりの「カラン」が多いという印象だ。語源が異なるのだろうか。英語の語源を調べるとなると、一苦労…と思うだろう。何でもない、検索結果をスクロールするだけだ。多分ラテン語の「喉」を意味する言葉かフランス語あたりが語源じゃねえの、的な事が書いてあった。
喉ってなんだよ?水が入っていくほうじゃねえ?大陸の人のセンスはわからん。しかし考えてみれば。これは単なる想像に過ぎないが、四大文明ぐらいの古い時代の風呂みたいなもん…動物の口からお湯が出ているようなイメージがある。王様の風呂。なんかライオン的な生き物の、牙の間からドバドバと。このドバドバが、ドバイの語源。いやいや、日本語でも「蛇口」じゃねえか。こっちこそセンスがわからんと言われそうだが…。
スマホ便利だって言ったろ?なんとインターネットが付いているから、こうしてお湯を待っている間に調べ間もが、って溢れとるやないかい!すみません嘘です。実際は溢れる前に気付きましたが、そこに自分が入る事を勘案すれば相当無駄に溢れさすことは必定なのでありました。
で。この時点でオチてもいるんですが、この夜はまだ続きが御座いまして。
この夜は、珍しくまだ夜の早い時間に風呂に入ろうとしたので、この余る湯で湯船入っている間に洗濯をして、干して寝ようという算段となりました。そこで、洗濯物集めてほうりこみ、電源を入れてまして、清廉な湯をバケツで洗濯機に汲みます。4~5杯ほど。ぽちっと運転開始。普段は注水から始まりますが、もうお湯が入ってるのですぐに回転始まります。これで、ただ無駄に流すことはなくなったと、よかったよかった。今度は自分がきれいになる番でして、体洗って頭洗って湯船でマターリkindleで読みたい本でもないかと探しております。洗濯機から水が抜ける音がする。ガッゴンジョワジョワ…洗濯が終わり、すすぎのターンが始まったところで、
洗剤入れてねえわ。
気付いたからには時間がもったいないので、風呂から出て、洗剤投入してやりなおし。ただ40度のお湯でゆすいで捨てただけ。風呂からそのまま溢れる水が、薄汚れただけ。がっかり。そりゃあね、慣れない手順でやったもんだからと言い訳もたつけど、いくらなんでも間抜け過ぎない?タイマー設定したわけでもないのに、洗剤入れ忘れたなんて過去にあったか?笑い話にはなるだろうけど、ただただ愕然としてしまった。そりゃあ、もっと酷い失敗をしたことある。もめ事に繋がるような事も、怒りを買ってしまったこともあるけど、なんだろうこの失敗の特別な脱力感。脳みそぐるぐる自転させて、一番近い感情を述べるなら「仕事じゃなくてよかった」という社会人みなさまが覚えたことのある感情になると思う。
何が悪かったというのかと言えば、自分が悪かったとしか言えない。いや、スマホか?インターネットか?カランか?洗濯機か?人類か?
問:上記の事例をうけて、その改善策となりうる提案が幾つかなされた。もっとも適切なものを下記の選択肢から選べ。
1. 浴槽の容量は建築時に決定されているのであるから、一定量でカランからのお湯の放出が自動的に止まるfaucetを導入するべきだ。
2. 洗剤を入れずに洗濯を行うことは一般的にありえないので、洗剤が入っていないことを検知すれば警告し、動作を一時停止する機能を持つ洗濯機を導入するべきだ。
3. 近年では家電製品をスマートフォン端末などから制御できることは一般的になった。ソフトウェアの仕様に無い動作はしないため、家事完了までのプロセスの途中が漏れる可能性がない。すぐに全面的に導入するべきだ。
4. 人間がミスをすることは避けようがないので、著者は家事代行サービスを積極的に利用し、どうでもいい語源を調べるとかいうクソ作業に没頭するべきだ。
5. 脱衣所の目に付く場所にチェックリストを用意し、スマートフォンにタイマーをセットしたか、洗剤を入れたか、などの項目を確認できるようにするべきだ。
2,3年前までは年明けから受験産業の広告が山ほど目にしたもんだけど、今年は全然だった気がする。上記の問題って真面目に考えたら正解って出るのかね?自分が受験生の事は、現代文なんて適当だろ、って解いてたな~。
5を解答したら退場。湯張りの問題がなければ洗剤を入れ忘れる可能性は低いのだから、1と2を比較したらお湯のほうを解決するべき。いや導入するべきって、賃貸住まいだわ。お湯の問題が発生したのはスマホを見ていたからなので、3で解決を図るのも良いが、自分が家事をしなければいいので4か。しかしいずれも現実的ではない予算が要るので、選択肢に解答ないわ。は~自分が悪いのヨー。
-
冷凍生姜シートをつかう
生姜が冷蔵庫でミイラみたいになってしまうことはあるあるだと思うのですが、鮮度を保つためにおろしてすぐにシート状にして凍らせて保存すると良いとのアイデアを発見し、実践してみました。いつのもように画像は一切ありません。
まず単純に生姜をおろします。薄く伸ばしたほうが適量をパキっと折って使いやすいとのことで、ジップロックのLサイズにいれて、のしていきます。冷凍庫にぽい。実際に出来上がったものを手に取ると、まず分量を把握するのが難しい。目分量で使うと割り切らないと、実運用に耐えないと思います。キッチンに秤があるようなガチ勢は別途工夫してください。ジップロックにマジックで罫線でも書けば、かけら幾つ分とか把握できそうです。あとは線に沿って折るための工夫を何か。
冷凍により鮮度を保つといっても、限界が来ることは明白。どのぐらいだろう?企業が研究の粋をあつめて作った冷凍食品でも一年行かない印象だけどな。どうせならその辺の期限を攻めたもので試したいが、今回は気にせず気ままに消費していく。以下の結果はおよそ2週間~1か月半時点でのトライアルになっておりま~。
ブリ大根
普通に美味しくできましたが、煮汁をすってしなしなになった生姜のカケラを頂くこともこの料理の醍醐味だと思います。惜しい。
冷奴
単純に豆腐に乗せてもすぐには溶けないので使いにくい。凍ったままのものを噛んでみると美味しくはない。豆腐に刺してみると見た目に面白い。針供養か。そこでお湯で溶かして、麺つゆをかけてつけだれにしました。生姜の風味が死んでないが適量を調達が難しい。すごくハードなつけだれになった。
茄子の揚げびたし
生姜シートのまま茄子に乗せてもみずっぽいし冷めてしまうので、事前に取り出して解凍しておくべきなんだろうか。だったらその時間で生姜をおろせばよいよね。ただ、必要な量が多いなら解凍のほうがはるかに楽で理に適っている。タレを別に用意してそこに生姜シートをいれて溶かすスタイルにすることで解決。白出汁とアツアツのお湯で冷凍生姜シートを溶いて、火を通した茄子にダバーでウマー
麻婆豆腐
元来は生姜をみじんぎりにして炒めて香りをつけるもんだが。凍ったままの生姜シートを放り込んで大丈夫かという思いがマッシモ。流石に大爆発しそうなので、火を止めてから少し入れる感じに。結果としてはあんまり美味しくもなく。いちおう生姜の味はしましたが、水分が出てしまうし。
麺類
少し細かく殴りつけた凍ったままの生姜シートをパラパラと。流石にその場でおろす手間に大きく勝ったが、麺類の薬味に生姜ってあまり使わないじゃないか。あつあつの揖保乃糸でやってみたら程よく冷めて良い塩梅。
ジンジャーエール
一からつくるのは大変ですので、市販のジンジャーエールに氷の代わりに入れてみましょう。モノはどこにでもあるウィルキンソンのジンジャーエール。タンブラーに注ぎまして、凍ったままの生姜シートをいくつかぽちゃんと。結果として美味しくはない。溶けてモラモラと底に沈むおろし生姜。氷の代わりにするほどの分量を入れてはいけない。だからってちょっと入れただけでは風味にさしたる変化なし。元来ジンジャーエールのあの香りはスパイス類のもの、生姜だけふやしたところで。
全部イマイチだったわボケエェェイイイイイ。
考えてみると、このアイデアは味わい云々ではなく、調理の手間と冷蔵庫の整頓にメリットがある。おろししょうがをつくったおろし金を毎回掃除する必要もなく、残った生姜にラップ巻いて冷蔵庫に戻す必要もなかった。なるほどなるほど。しかし、生姜をおろして使うって、その機会は思ったほど多くなかった。
するってえとニンニクはどうかなと思ったが、にんにくをおろすのはかつおの刺身ぐらいしか心当たりがなかったのである。生姜より皮をむくのも簡単だし、房単位で分量の調節もできるし、皮に包まれたまま冷蔵庫に保存できるので、使いかけの生姜とくらべるとあまり鮮度どうこう気にしないのではないか?なるほどなるほど。
試してみて損はなかったけど、まだ大量にあまっている冷凍生姜シートはどうしたものか?ネットで生姜の消費レシピをさぐると、つくだ煮とかシロップが出てきますが冷凍シートでは転職できませんね。あゝ…こちらからは以上です。
-
めし短観2022年12月
セブンイレブンで「わさびめし」なるおにぎりを発見。出汁を効かせて、全体的にワサビの風味といった感じ。なかなかおいしい。
「蒸しホタテ丼バター醤油風味」なるものをコンビニでお買い上げ。小ぶりだがいちおうホタテはホタテだった。バター醤油風味があるといえなくもない程度。とうぜん美味しくはなかった。
「えんがわわさび巻き」なる手巻きおにぎりをコンビニでお買い上げ。これは駄目だと言えるほどの商品で残念。中に何か入ってはいたし、微かにえんがわっぽうい味わいもあったが。コンビニ飯で海産はこんなもんですよね、さすがに。
「森の燻製ナッツミックス」なるものをお買い上げ。ミックスナッツではなく、ナッツミックス。おいしい。パッケージが謳う通りに香りがあるが、こういうものは何か飲み物と一緒に頂くので、その相性が出るかもしれない。本品はフルーツ系には合いそうにないかな~。お酒飲む人はどうだろう。この酒は合うとか合わねえとかありそうだな。
https://md-holdings.com/product/list5/4977856201799.html
プリングルズのたまごサンド味なるものをお買い上げ。なんだそれとツッコミながら買ったような感じで、期待感は薄い。味わいは…確かにそれっぽい風味ですね、としか言いようのない。何味だって大差ないですけどね、サワークリームオニオンのやけくそ感は好き。
ひさしぶりにランチを他人と共にする。出先の社員食堂を除けば3年ぶりだろうか…と書いてすぐ、今年の夏おわりに一回ランチあったなと思いだす。とにかく、たぶん3年で2回ということ。当然ゼロにもできた。出勤の機会が減っているんだからそうなる。個人的にはおうち籠りはすごくありがたい。こりゃランチ需要で稼いでいたお店はたまらんだろうなと思うけど、いっぽうでめし配達自転車の多いのなんの。この配達めし、自分も一度試してみるかな、とおもいつつ、実行に移さず。
年越しなんたら、今年はどうしようか。定番、年越しそばの縁起については「細く長く生きる」という旨を存じていたんだけども、他にもあるようだ。側とかけて「来年も共にすごしませう」といったもの。麺が切れやすいことから、「今年の災厄を断ち切る」というもの。それはそれで大変に宜しいが、ひとりで暮らすようになってからは蕎麦以外に、うどんやカップヌードル、はるさめなんかを試した。冷やし中華もやったかな。どのみち、そんな心を込めて食うには至らず、だったら面白半分、駄洒落でもこじつけでも、なんぞないか。ネットに情報を求めると、沖縄ではいわゆる沖縄そばを食うとある。沖縄そば…そこらで売ってる?Amazonさん?また世界の大晦日で何を食うのか、という情報もあった。あったが、真似できそうなのはブドウを12粒食うとかレンズ豆を食うとか。真似しても味気ないか。さてどうする。
答えは2023年1月の短観を待たれよ。良いお年を。