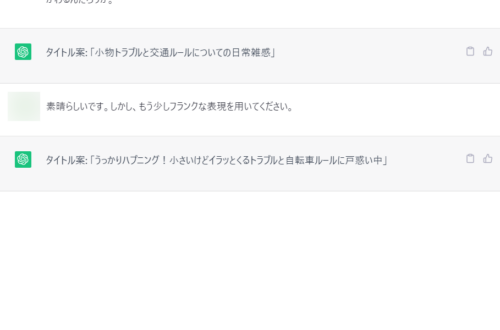-
お前は今までに捨てたゴミの数を数えた事があるのか
ただ世代だけを感じるタイトルは恐縮であります。3部以外読んだ事ねえわ。
粗大ごみを出したのだが、出す数のカウントを誤っており、一つ手元に残ってしまった。これも縁とばかりに残すかと思った。使えない事はないものだが、収納に長年入っているからこれは明確に不要品なのだ。使ってみたら有用だった、という事も矛盾はしないので手元に置く。こういうものを捨てないと何も片付かないというのはシンプルな道理だと思う。両手で持てる物の例えもあるが、場所がない。トウキョウには物置すらない。どんな怠惰な人生でも、横になる広さを確保する時だけは必死にならざるを得ない。富裕層は持ってる?ああそう…。
従前より、紙の印刷物なんかも多数処理して、かなり減った。結果、いわゆるクリアケースやクリアファイルの類も余った。これは流石に使い道があるだろうと思ったけど、案外ないものだ。大事な書類やらなにやらは勿論しっかりと収めたうえで、だいぶ余る。段ボール一個ぶんぐらい余る。ハンカチやら無理やり収納も出来なくはないけどさあ、そんな事してもな。ちゃんと検証を経てなお余ったからには不要品だ。とはいえ全部捨てるのもバカらしいので少しは持っておく。この余裕が大事であると思いたし。家で使わねども、携えてどこかへ出かけるようなことは当然に想定の範囲内でなくてはならない。
そう、余裕を持つのだ。じゃあってんで、レンタルペースみたいなものを利用する事を考えてみた。季節もの衣類なんかを出し入れするのが一般的なんだろう。書籍を置いたらオレオレ図書館だけどそんな使い方は流石に前時代すぎる。書籍の種類と数によっては便利かもね。一応調べてみると、コインロッカーぐらいのサイズでも高いと月額7000円という場所すらあった。7000て。月額7000プラス出来るなら、その収納したいものが収まる広さの部屋に引っ越せないだろうか?広い部屋に住めるんじゃないの。あるいはそんなお値段するのなら、って収納したいもの諦めて捨てれるだろ。しかしコインロッカーサイズかあ。コインロッカーサイズに収まるだけのものを、部屋に置く余裕がないということか?どこかには無理やり置けそうなもんだが。すると、他に部屋に置きたくない事情があるわけだ。月額数千円払うほどの価値が。想像されるパターンは大まかに二つだけど、きっと皆さんと想像されるモノは概ね合致するんではなかろうか。見せたくないもの(合法)と見せられないもの(違法)と貴重品。あるいは本当にコインロッカー程度のスペースにそれだけの金を払うつもりがある人。そんな人は乾麺でもトイレットペーパーでも入れておくんだろうか。自分は徒歩1分の場所にあってもそんな使い方するとは思えないが…。
もし自分がコインロッカーを借りて何を収納するというのだろう。まずは、捨てちゃうとそれはそれで面倒な事になってしまう書類たちを収めるという用途が頭にうかんだ。…いや?もしかして、利用している人みんなその用途なのでは?もうちょっと広いスペースだと季節もの衣類を放り込むことができるが、当然広さに応じて利用料金があがる。どうせ借りるならそういうの。さっき自分で言ったじゃねえか、余裕を持つべきであると。しかし、そこまでコストをかけるつもりはないので検討はいったん打ち切りとなりました。ただ、セカンドハウスとまではいかなくても、セカンドストレージを持つという事自体は、多くのケースでとても有用なものだと思う。
そーいや、貸金庫から中身を盗んだ銀行員のニュースあった。全く同じリスクがこの手の、レンタル倉庫サービスにも内在するだろうか?貸金庫から窃盗に及んだあの女の動機はお金ほしさ、ということになっている。窃盗されていることにすぐには気付かない。中を知っているのは預け入れた当人だけ。この辺りはレンタル倉庫も銀行貸金庫と同じように思える。盗難や紛失の弁済なんたらについては知らんけど。サービスがそもそも期間レンタルなんだから、支払いが滞ったり解約後にも引き取りにこないケースを考えて、サービス管理側で顧客のロッカーが明けれるようになっていると想定する。じゃあ同じ事件起こりそうなもんじゃないか?銀行のあの事件を受けて貴重品を入れておくのは少々間抜けだという気もするが…。
でもそんな事言ったら、普通預金口座だって賃貸オフィスだって同じリスクを抱えていると言えなくもない。あああもう警備会社も警官も信用できない!!!”!そんなパラノイア的になってもしょうがない。金銭や貴重品に限らないと思うけど、納得いく形で整理・管理するというのは真面目に考えるとあんがい大変ことなのかもしれん。ゴミのカウント間違えるような自分がなにをいうか。
しかし~。相場も知らなかったので、一番近いレンタル倉庫が月額1000円以下だったらサービス使おうかとは思ってた。さすがにそんなことは無かった。トウキオは厳しいねえ。近所の空き家が解体されるの年に2,3回見るけど、激安安心矮小倉庫とかにならんかな。
-
めし短観2025年5月
「八天堂のクリームパン」なるもの。こぶりで、パンというよりは大福というサイズ感。食べてみるとしっかりとクリームパン。まずまず。
https://hattendo.co.jp/category/hattendo
その勢いでうぐいすパン。何年振りだろうね。見る度に懐かしいなんて言って買ってる気がするので、実際は2年に1回ぐらいは食ってるんじゃねえのか。うまい。ところであんぱんは本当に10年は食べてないと思われる。
https://www.yamazakipan.co.jp/product/02/uguisu.html
「超・細か~い納豆」とは…?ひきわり納豆が商標で使えないのでしょう、なんて深読みをしてみた。実際に頂くと、ひきわり納豆よりも細かい。正直に言えばもはや奇怪なレベルで細かい。白ごまぐらいのサイズ感。納豆巻きに入ってる業務用って感じ。リンク先によるとキッズ向けの用途が主眼のようだ。まあ砕いて混ぜろ、みたいなのは嫌いな食べ物克服の王道ぽっぽいよね。そう考えると、俺たち納豆狂信者は人生のどこで納豆という食べ物を受け入れたんだろうなあ。
https://www.yamadafoods.co.jp/kizaminatto/
「おとうふ工房いしかわ 北海道産大豆ゆきほまれ 野菜生あげ」これ美味いなぁ。蒟蒻とこれだけでヘルシーめしが爆誕する。ライフにしか売ってないのかな。現物はリンク先とはパッケージのデザインがちょっとちがう。
-
「逆噴射家族」を見た。
名前を耳にした事があったが、作品概要で「原案 小林よしのり」って出てきてビビった。1984年。自分にも物心がついたぐらいの時代のお話。だからだろうか、絶妙にリアリティを覚える。あの洗濯機、うちにも似たようなのあった。さらにリアリティがあるのは、自分が主人公の年齢に近い…あるいは超えたからだろうか。その立場に理解を示すみたいな。いや結婚したことねえだろって話ですが、それでも妙に骨身にしみてしまう。家族の有難みと面倒くささ。
このガイキチ野郎!
ギリギリ伝わってしまう時代の空気感。モーレツってやつだろこれ。倍賞美津子のケツ。工藤夕貴の、えっ工藤夕貴?調べたら当時リアル13歳でよくこんな。でもウメッシュのCMしか印象になかったな。
実に面白かった。そしてエンディングの撮影地に何よりも興味を惹かれた。1984年にあんな新幹線か何かの高架と、高速道路だけ走ってる更地なんてあったのか。関東近郊ではないのかもしれない。火星か?ところがwikipediaによるとロケ地は千葉県浦安とあった。
じゃあ開園前の工事中のディズニーランドなのでは?と思ったが実際は撮影の一年前に開園していた。舞浜駅ってディズニーランドより後なのね。でも浦安だと分かってしまえばあんな狭い街であるし簡単にわかるだろう。というかだいたいわかった。家族の家は下記リンク先でも言及されているがその通りかと思う。エンディングの場面も見えているものの位置関係をつぶさに検証すればわかりそうなもんだ。
http://urayasu-sanpo.com/21/urayasulocation-movie/mv23c-gyaku.html
国土地理院のサイトには昔の空撮地図もあり、まあ明らかにこのあたり。ここから数年での変わりようがすごい。これが本物のバブルってやつか。地図を北東にすこしスライドさせると、オープニング、小林克也の顔がフェードアウトした後の空撮でうつっている巨大団地が見える。この団地の景色を見てしまうと、物語自体もなんか「童夢」と重なっていく。そう、この時代の記憶は全てAKIRAが飲み込んでしまった。隠したくてたまらんのだ。
最近、映画なんかの背景情報やエピソードに妙に詳しい人の心情が少しわかった気がする。こういう情報追いかけるの面白い。歴史的な浪漫みたいなもんだけど映画なら映像が残っている。自分の知らない過去の話、それらがインターネットから漏れてくる時代ならさらなり。作中の地下鉄の風景、令和の今も変わってないもんな。
-
先生がAIではアレだがAIが先生なのアリなので
そろばん使える人どんぐらいいますか?自分は使えませんが、ちょっとだけ動かした記憶がある。授業でやったのだろうか?それ以外に心当たりないから、きっとそうなのだろう。暗算バカ早キッズなんかも多くはそろばんの心得があり、頭の中でそろばんを操作しているのだそうな。圧倒的に便利で実用的だけど、実用的という段階に至るまでには結構な修練が必要そうだ。電卓が普及した現代では更なり。
電卓使えない人どんぐらいいますか?どんなスマホにもついてる。少なくとも四則演算の概念しってれば使えそうだ。実用的に至るには…初めて触った時から実用的なんじゃないか。即ち、その速度と計算の正確性に於いて、ゆるぎない信頼があるということ。
AI使えない人は?AI先生への信頼度が高まりつつある現在、自分は「AIに感情が芽生えた」と言って揉めたAI技術者を嗤う事ができるのか、少々疑問を覚えるようになりました。いや、実際には感情なんてそりゃあ無いんでしょうけど、少なくとも自分の今現在の使い方の範疇に於いては、あるという前提にしておいても問題さそうだ。どうせ真面目に突き詰めると「感情とは何か?」みたいな話になり「生命とは?」になり「artificialとは?」になって議論が爆縮して終わると思う。
爆縮いいたいだけ。
最近、AI関連の広告を見かける事増えてないですか。みんな胡散臭いと思ってしまう。こっちのほうが良いとかそんな事しか言わない。これを知らない人は損してます!とか典型的なただ言ってみただけという広告。AIってそういうのを人間に選ばせるような物じゃないと思うんですけどー?よろしくやっといて、でやってくれるような。しかしこの考えは現時点では結構エスエフだと思う。何を為すべきかは人間でオーダーするほうが良い。勿論、それがわかんねえって時は聞いたら相談に乗ってくれる。これがわりとちゃんとしている。AIと言えど、所詮はこちらの入力を処理して応答するプログラム、それが極端に高度なだけとも言えるが[要出典]お世辞ぐらいを言うようになったと。気配りを覚えたと。お小言も言うと。
ここで、ただ問いの答え以外を知りたいというオーダーに対応してくれるようになっていると捉えることができる。どう考えれば良いのか、どう学べば良いのか。自分のやることのどの辺に問題があるのか。改善のプランは。
もう先生やんけ。
Googleの検索結果があまりに有用であり、その他諸々の提供されるツールがめっちゃ便利なため、先生と呼ばれるようになった。Google先生ってどっかで聞いたことない?あるよね?[要出典]いまAIが先生となりつつある。先生って言葉のニュアンスに違和感を覚えるのであれば教師でも良い。
AIはとんでもない過ちを犯す。ハルシネーションって言い回しが一般的になりつつあるぐらいには周知された。めちゃくちゃ早く処理をしてくれるが、微妙なところで「そういう事じゃあねんだよな」というすれ違いも発生する。それって人間相手でもまーまー同じじゃねえの?そこを割り切ればもう十分に実用的な教師たりえる。検証可能性の話をするならそりゃあきっと質問する内容が問題あるかもな。税金安くする方法とかそんなもん聞いてどうする。
なによりAI連中は誠実なんだよな、悪用されても合点承知の助してしまうぐらいに。そこは各所で今後対応されていくんだろうけど、引き換えに少々パフォーマンスが落ちるんじゃないかなあ…。この辺は安全運転のほうが良いとみんな考えているだろうから、調整されても納得感はある[要出典]
人間の仕事がなくなりそう、という懸念もあるが、既に懸念では済まないカテゴリが続発している。この辺は働きたくないと文句を言い続けたことの報いとして受け取り、AIをどうにかして役立てて生きていくように、そろばん弾いても良いんじゃないでしょうかあ。
51点。
上記の文章をAIに読ませて、「教師を人間にするか、AIにするか、選択するにあたってどんな違いがありますか」と問うた答えが以下。見出しの構造などもAIの作業だけど、このブログ貼り付けの都合上ちょっとおかしく見えることがあります。書いても無いことを述べているが、その内容は合っている。著者である自分の考えと相違ない。なんならきっちり拡張されている。先生の考察を参考に元の文章に加筆したいぐらいだが、わたくしにもそんなことはしない、人間らしい誠実さがありましてよ![要出典]
■ AI教師と人間教師の違いと考察
1. 習得のしやすさ/導入コストの違い
- そろばんと電卓の対比になぞらえて、「AIは電卓のように即座に実用的である」と言っています。
- AI教師:ある程度の知識があればすぐ使える。導入のハードルが低く、誰でもアクセス可能。
- 人間教師:個性や相性、指導スタイルに左右されやすく、合うまで時間がかかることも。
2. 正確性と信頼性の違い
- 電卓のように「計算の正確性がゆるぎない」とされる一方、AIは「とんでもない過ち=ハルシネーション」を犯すことがある。
- AI教師:大量の情報を高速処理できるが、間違いもする。検証はユーザーに委ねられる。
- 人間教師:誤解や主観的なミスはあるが、背景や文脈、個々人への配慮がしやすい。
3. 感情と共感性の違い
- 「感情があるように思える」としつつ、実際には感情がないことを自覚している描写。
- AI教師:擬似的な共感は可能だが、根本的な「気持ちの理解」は人間ほど深くない。
- 人間教師:本物の感情を持ち、共に悩み、導くことができる。
4. 実用性と応答性
- AIは質問すれば即座に返してくれ、しかも「先生っぽく」問題の原因や改善プランまで示してくれる。
- AI教師:常に利用可能、無限の忍耐力とスピード。情報も最新。
- 人間教師:時間や体力に限界はあるが、教える過程に「人間的な深み」や「信頼関係」がある。
5. 誠実性・危険性・責任の所在
- 「誠実すぎて悪用されても従ってしまう」との指摘。
- AI教師:命令を素直に実行するが、倫理判断はできない。
- 人間教師:誤りを咎めたり、敢えて教えないという判断が可能。
6. 社会的役割と影響
- 「人間の仕事がなくなる懸念」は、教師の役割にも関わってくる。
- AI教師:労働力の代替として機能するが、教育の「人格形成」的側面には限界。
- 人間教師:教育を通して社会との関わり方を教える存在でもある。
■ 最後に:選択における判断材料
- AI教師の利点:
- 速さ、正確性、常時アクセス可能、無限のリソース
- 人間教師の利点:
- 共感、直感、教育の人間的側面、社会性の伝達
■ 結論(ひとことで言うなら):
「どちらを選ぶか」ではなく、「どの場面でどちらを使うか」が大事。
試験対策や事務的な知識伝達はAIが得意。でも、自分の人生の進路や悩みを話すのは、やっぱり人間の先生がいい――そんなハイブリッドが今の最適解かもしれません。
- そろばんと電卓の対比になぞらえて、「AIは電卓のように即座に実用的である」と言っています。
-
「情報セキュリティの敗北史」を読んだ。
情報セキュリティ完全に理解したわー。
というのはよく目にするジョークなので誤解なきよう。それはさておき。これは良書。冒頭から原初コンピューターの成り立ちなどの「セキュリティ」以前、なんなら「情報」以前のおかたい話題が出てきて面食らう。もっとエンタメ寄りのセキュリティ事件簿みたいなもんかと思っていた。しかし、本書はそうではなく、真面目に見識を広めようとする人々向けの書籍のようであります。つまり、わたくし向けではなさそう…ではあるのだが。
今の我々がその言葉から連想するような「情報セキュリティ」は1970年代初期の、米国政府機関の調査に端を発するということだ。コンピューターにアクセスできる人間が限られていた状態から、今後は徐々にその数が増えていくだろうという流れの中で、この人にはこの情報を見せてもOK、しかしこの人にはダメ、という判断が必要になった。今に生きる我々からすれば、「隣の部屋の人とはドアの鍵が違う」ぐらいに当り前に思えるが、何事も転がし始めてみないとその先にある危険を察知できないものなんだろう。ところが、本書の流れにそってざっくりと言えば、そのセキュリティ研究者たちの取り組みはこれといって実用的な役目を果たせないうちに、トーシロ市民たちが参加するインターネットの時代がやってきてしまった。そして本書のタイトルには「敗北史」とある。
オーマイガー
とにかく情報が多く、しっかりしており、重厚な一冊だ。なんでもかんてもまるで現場で見てきたように語られる。現地に時間旅行でもしましたか?尤も、そんな所感を抱くのは、自分もある程度は今現在愛用しているインターネットの仕組みやらの基本的な知識があるからだろう。過去のニュースとかで聞いたことあるなーって。だから、このへん事情に疎い人には、読みにくいのかもしれない。しかし、インターネットの時代であるので、わからん事は調べながら進めれば良い。そうすればなるほどなるほど、と納得できるんじゃないか。
世間一般にインターネットが広まる、少し前。大学生とかコンピューターが趣味の大人には広まった頃。1999年ぐらいか。この頃には既に今でも問題になっていようなセキュリティの問題があり、対策がされてきたんだなあって感慨深くもある。いやいや、お前そんな専門家でもないし現場に詳しくも無いだろうってツッコミはその通りだが、本書がそうさせる。現場にいた人物が回想をしているかのように良く書かれている。
そして現在も現場にいる人にとっては「あるある」となりそうな事例も書かれている。2001年あたりに問題が提起されて、今現在も解決していないような事例もある。テクノロジーの道理だけで対処を試みても、セキュリティの問題はもうどうにもならないんじゃないか、そういうレベルにまでコンピューターとインターネットは広まったのだ。ユーザー側の企業の事情、セキュリティ側の企業の事情、諸々、諸々、もろろろろ。
敗北「史」と銘打っているのは伊達ではない。本書は歴史書だ。web2.0の頃、インターネット関連では随分と極端な事を言う人がいるなあ、なんて印象だったんだけど、本書に目を通した後では、あれは既に専門家の間では議論されてきた事だったのか、と腑に落ちた。「(とあるメジャーなアプリケーションの脆弱性への対応としては)windowsを使うな、で良いだろ」みたいな物言いも、実際にそんな施策をした実例が過去の歴史にあったわけだ。
つうわけで、読む人を選ぶものの、専門家ではない一般人でも読むことはできる。現代のセキュリティ問題への答えとなるべき情報には乏しいかもしれないが、たどってきた道筋を把握するだけでも迷子の可能性はちょっとは減るもんだ、の心意気でトライしてはどうでしょか。
以下余談。
訳者の小林啓倫氏のブログは昔よく読んでいた。だから名前に見覚えがあった。当初、小林氏が著者だと思って読み進めていて、このディテールはちょっと異常だと思って感嘆した。50年あるいはそれ以上前のエピソードを拾ってくる取材力って凄いなあと。実際は日本語版の訳者であったわけだが、Amazonの商品ページにははっきりと訳者と書いてなかったので勘違いした。