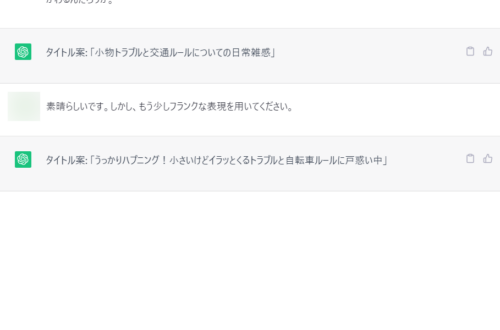-
芸人枠
近代麻雀を読んでいたら、S氏のコラムで以下のような事が書かれていた。
ところで、あの顔三味線をひいていた芸人は五期売って毎度ビリあたりにいても、戦力外通告を受けずに五年間チームのために負け続けている。
近代麻雀2023年6月号 我れ悪党なり vol509冒頭の「ところで」以前には、Mリーグがユル過ぎないかという意見が前置きされている。この芸人とは明らかにH氏だ。成績はその通り、ひどいものになってしまっている。「そもそもプロでもないのに何で参加してんの?」っていう人もいるだろうけど、昔から麻雀の腕は確かだ。競技麻雀に触れている機会も多い。なんだっけ、片山まさゆき氏のあれとか。…ほんとなんだっけな…。
だから、例えばテレビタレント関係者から誰か引っ張ってこい!という話になったら、H氏はまあまあ真っ当な人選なんじゃないかと思う。畑正憲氏(ムツゴロウ)では既にいろいろ尾ひれがついた話が多すぎるし、風間杜夫氏とか児嶋一哉氏(アンジャッシュの無事なほう)も競技麻雀が出来る人だと思うが、だからってMリーグに本腰を入れれるだろうか…。1プレイヤーとして全うしてくれるか疑問。
それでも、H氏が麻雀プロ長年の憧れであった、「本当のプロ」として戦える舞台にプロを差し置いてまで出るほどかと言われると…現時点の結果では何の擁護もできない。「顔三味線」と言われてしまっているのも、Mリーグ見てる人なら察せられる何かあるでしょう。四人で向かい合って競っているのだから、仏頂面で淡々とテンポも変わらないのが強い。…強いというか、情報を相手に与えないというスタイルにはアドバンテージがある。
麻雀をある程度遊ぶ人なら誰だって、そう思う。淡々として進めるのがとてもプロっぽいんだよね。これは長考するだろうな、みたいなところでスッと最適解の打牌したら恰好いい。逆に役満あがってガッツポして喜んでたら嫌だろ。競技規約を順守するとか、対戦相手へのリスペクトもさることながら、仏像プレイはプロの技量の一つだと思う。だからこそ、Mリーグみたいにいちいち顔を抜かれるカメラ付きで中継していると、国士頭ハネされたら放銃した人のほうを睨むとか(怒りが出ますよ)、人としてちょっとこらえ切れないものが垣間見えることがある。これが面白いんだわ。
麻雀業界では、一般的には悪意を以て嘘のリアクションで人を欺こうとすることを三味線って言って、モラル的な禁忌の一つだと思う。これは仲間内でもダメだし、フリー雀荘でも出禁案件だぞ😡H氏が悪意を以てやっていることは無いだろう。でもプロの間では、あまりにもたびたび、顔や所作に顕れること自体が良くないと思う。…正論の筈だけど、話の流れで槍玉にあげようとしているように取れてしまう。「五年間チームのために負け続けている」ってどストレートな物言いが加わって、なおさら槍玉に見えてしまう。なんならトータルでぶっちぎりに好成績の麻雀星人だって、どちらかと言えばリアクションは大きいほうだ。
何度見ても面白いな。これは良いのかと聞かれれば、「自分の手牌とかを欺こうとしているわけではないからセーフ」で自分は全然納得できる。なんにせよ、リアクションは全部ペナルティってのも無理があるんだから、H氏ぐらいのは別に良いんじゃないかって思う。誰だって何かしら癖はあるもんだし。
「芸人」だとお笑いの人をイメージしてしまうけど「芸能人」だから「芸人」呼ばわりは間違ってないと思う。H氏加入の経緯は知らないけど、しょーじき、ある種の保険という考えもあったと思うんだよね。なんか一般的な知名度あるやつも入れとくか?って。そういう判断がされるのは、新興イベントでよくある話だと思う。良くある話というその裏返しとして、どうやっても芸人枠の参加者として見られてしまう。
Mリーグは今のところ成功しているように思えるし、先日のBEASTジャパネクストのオーディションの内容と盛り上がりを見ても感じされるように、そういう考えはもう要らなくなったんじゃない?Mリーグはもっと圧倒的な壁であってほしい。俺でも入り込めるんじゃないか、なんて勘違いをしたほうが恥をかく世界であってもいい。スラング的なニュアンスを含めての”聖域”では、ちょっとアレな世界で嫌だけど、この壁を超えれば何かが許されて何かが許されなくて…少林寺みたいな世界か。もうちょっと現実的に近いもので言えば、将棋棋士の世界かしら?なんて考えていたら、将棋棋士と元テレビタレントが参入することになって、本稿は所詮は野次馬枠の意見、裸単騎の一人聴牌にて流局です。
麻雀プロの肩書以外は認めない!なんて考えは今時そぐわない気もするし、自分もそう考えないほうが良いと思うけど、それでも何か色眼鏡で見てしまっているんだろうな。自分だってMリーグ参加者でも、始まるまで名前知らない麻雀プロの方が何人も居た。ほんとツウ気取りの野次馬枠でしかない。
-
めし短観2023年6月
暴君ハバネロのコンビニブランド別パッケージ版かと思ったら、『超』暴君ハバネロだった。ノンシュガーのカフェオレで流し込むも、見事にお腹を下した。
https://www.family.co.jp/goods/snack/4820154.html
コンビニブランドの中では特殊容量詐欺以外の点では評判良さそうなセブンイレブン。…の、アラビアータ。にんにくの風味が効いている。にんにく自体もトマトソースの中から顔を出す。大変に美味しいが強烈。こういうのをパンチが効いてるっていうんかね。これを前出の超暴君と同じ日に食べたのはやりすぎだったかもしれない。
https://www.sej.co.jp/products/a/item/340147/
堅あげポテトシリーズに「アサリの酒蒸し味」があったのでお買い上げ。カルビーのサイトに載ってないので闇商品。うへへ。こういう時は闇芋をキメたとか言うのだろうか。お味はおいしゅうございましたが、自分にはちょっと油が強すぎるんだよね堅あげポテト。冷えた麦茶よりもあついほうじ茶なんかで頂きたい。載ってないけど一応リンクしとこう
https://www.calbee.co.jp/products/select/?cid=2
卯の花を作った。こんにゃくが売っておらず、油揚げを買い忘れ、具材が人参とカマボコだけになった。何か追加でいれようとコンビニへ行くも、こんにゃくも油揚げもない。その場でシイタケを思いついたが猶の事売ってねえわ。結果、鳥のエサみたいなものを美味しく頂いた。
体調悪いときは粉ポカリ。薄めに作ってがぶがぶ飲みまくる。ワクチン副作用の発熱の時なんかに消費していたんだけど、幸いにしてそんなに出番は多くない…が、ハバネロ野郎により最後のストック半分ほど消費。残しても仕方ないので作りきってしまって、薬局で新たなストックお買い上げ。の、ときに、経口補水液が目に付いた。あのOS-1ってやつ。試したことないので、こちらもお買い上げして一本いただく。かなりうす味のポカリスエットに塩を足した感じ。美味しくはないのでちびちび消費。逆にこんなもんガブガブ飲んで大丈夫なのか?と調べたら、商品サイトの圧倒的充実ぶりにドン引きする。一分の隙の許さんよ、という気骨を感じる。
-
「MONSTER」を読んだ
浦沢直樹のコミック、…と但し書きしないと同名の作品ありそう。どうかな。大変に面白かった。堪能した。
王道の雰囲気。例えば、銃声のコマを経由して場面が切り替わるというのもよく見ると思うのですが、これを何度使うねんって。でた~~~wwって愉快になってきてしまう。何度も「本当の恐怖」なんたら~とかいって展開が進むのは、ドラゴンボールの戦闘力インフレを連想する…!!!!!!!!!!!!それらが不快なわけでもないけど、そういう造りのジャンルってことなんだろ。
Freedom is slavery
作中の世界観、および発表当時のリアルご時世で「東西対立」という問題が背景にある。東側って何か怪しいことをやっているという王道テンプレがあると思う。自分はそんなに多くの創作に触れたわけではないですが、ゴルゴにしろなんにしろ、敵役?は東側という印象がある。例えば、共産主義体制の個性や人権を軽視した権力によって〇〇〇が生み出された!的な。史実も概ねそんな感じだったんだろうなあと想像する。自由が生み出すMONTERもおっかないというのは現実世界の学びではありますね。
War is peace
世界情勢をベースにした物語というのは、創作に於いて良くあるものだと思うけど、2023年にはどういったものがありえるだろう。インターネットやSNSという言葉が浮かんでくるけど、この20年ずっとそうだろって話だ。この3年ぐらいだと、コロナは世界的な出来事だったけど、ウイルスや疫病は類似の作品が過去にたくさんある。世界が平和で…人々が貧困な暴力におびえていない世界が長年続いた結果、そんな物語を作ってもリアリティがなくていっそ退屈だったら良いのに、現実は人々が貧困や暴力におびえ続ける世界しか存在せず、うまれる物語には毎度の説法臭さ。
Ignorance is strength
本作の最後の舞台。雨の降る田舎町。2023年だったらこの筋書きにリアリティが無くて退屈か?そんなことはない。戦時中でもない街中で、子供たちが逃げまどいながら銃で撃たれる
コマ世界はここにある。世界の東側、壁の向こう、隣の部屋の中、インターネットのプロトコル。MONSTERは「どこにいるのか?」ではなく「誰なのか?」という疑念が人々を恐怖に縛り付ける。誰なのか。それはきれいな顔をしている、大人しい、しかし社交的、要するにあなたも含めた普通の人。こんな数十年来のテンプレが、リアリティを失う事がないのは、あなたも身に覚えのある、世の中の本当の事だから…か?「自由が生み出すMONTERもおっかない」という学びは信頼できるかね。恐怖から逃れる術とやらは、誰が誰に伝えたのか。あなたに伝えたのは誰だったか覚えてる?きっと、きれいな顔をしていて、大人しくて、カーリーヘアーで、眼鏡をかけた初老の漫画家。
恐ろしい話で御座います。
-
「はだしのゲン」を読んだ
実は読み終わってもうずいぶん経つ。しばらく、感想文をどんなふうに仕立て上げたもんか迷っていたら、広島でG7が行われる予定と知り、んで、あっさり終わってしまった。もう夏だギギギ。
はじまりは少年ジャンプの連載作品だったということだ。主人公たちもキッズであるから、元気いっぱいだ。苦境にめげず立ち上がっていく姿を描いた。…という情報に偽りなく、確かにそういう作品だという感想を抱いた。ドキュメンタリーとはちょっと違う、漫画の形なわけだ。作者が実際に被爆経験をしたという事もあり、もっと悲壮な感じなのかと思っていた。筋書きは戦禍の悲劇ではあるのだが、なんかこう、とてもエネルギッシュだ。エネルギーに溢れるままに、「君が代反対」とか「天皇の戦争責任」とか登場してウッとなる。これは作者本人の強い主張のようだ。
少年ジャンプでの連載を終えたのちに、本作品は数誌を転々として物語を終える。その数誌のラインナップと、1970年代という時代で、何かこう色眼鏡を通して眺めてしまう…。戦中は勿論、1970年代だって実際に知りはしない。昨今、毎日のように戦場の映像が流れているロシア-ウクライナ戦争だって、自分には”知っている”といえるほどの体験は何もない。
小学生の頃。ある老先生がこんな話をした(うろ覚え)。アメリカの空襲で街は焼けたが、お寺なんかは焼け残った。アメリカは日本の文化財を狙わずに攻撃をしていたんだ、と。その姿勢に感服したと。子供の頃には、「へー」ぐらいの話だったんだが、すこし考えてみればとんでもねえ(censored)の与太話だと思った。じゃあ防空壕なんか掘ってないで寺を作って寺に逃げればいい…。それにしたって、寺なんて幾つもあることだろう。3月11日の東京大空襲は、夜の攻撃だった。当時、夜間に寺だけ避けて爆撃なんてできた筈はない。ご丁寧にもナパーム弾だったと記録されている。(※wikipediaによれば1944年の11月にはレーダー照準で夜間爆撃テストした、と記載がある…)
ただ…その教師の体験では、真実だったのかもしれない。実際に寺に逃げたら助かったということがあったとしても、不思議ではない。何度か寺の境内で空襲を生き延びる度に、確信に変わったのかもしれない。実際は…うまく表現できないけども…たまたま?それがたまたまだろうと何だろうと、神仏のご加護を感じるぐらいのエクストリームな状況だと思う。だからってそれがアメリカの手心だと宣うのはいったい何なのだ。(censored)か。当時で戦後40年も過ぎ、教職が子供に語ることにはどういう意図があったのか。愛と平和の複雑さでも学べと言いたかったのかもしれない。
そんな事はすっかり忘れて、わたくしはぼんやりと大人になった。
大人になって…世の中には、この国や社会が崩壊することを望むような人までもいると実感することもある。さっきの教師がそうだったのか?こんな数十年前のうろ覚えエピソード一個で疑わしいとか言い出すわけではないが、”そういう”考えに近い人たちが、血気盛んに国際的テロまで起こした時代があった。自分の体験はそれから少し後の時代の話だ。ありえるじゃないか。恐ろしい。寺に逃げろ。
しかし、戦争と言う苛烈な体験をしたという事実に頭があがらない。「寺だけ無事だなんて、そんなことあるわけないじゃないですか」「黙れクソガキお前は黒焦げになった妹を素手で掘り出したことがあるのか」自分の世代だと祖父母がみな戦禍を体験している。暴力に晒されること以外にも、戦争が終わってみれば天皇は人間でしたテヘペロとか、なんかこう…いろいろ信じられない激変があっただろう。田舎の親戚の墓地の隣には、戦場に散った方々の共同墓碑があった。ずいぶん古いものだで風雨にさらられて土台には苔が生えている。どなたも未来ある若者だった筈だ。できあがったのは戦後だろうか?戦中であれば、軍神と崇められたんだろうか?
何が本当かなんて、わからない。少なくとも当時はわからなかった。そこら辺の誰かの与太話や思い込みと合致するわずかな事実が、とんでもないデマになって広まったりすることは、今日でもなおある。戦時中の民間人の勇ましい記録も残っているが、本当に全員が全員勇猛果敢に戦おうとしていた筈なんてない。本作の主人公の父みたいに、本土に戦禍が及んでなお戦争には反対だという人だって、いたんだろう。嘘をついていた。お国のため、自らのため、家族のため、世間体のため、死んだ若者を奉るため。しかしリトルボーイとファットマンに嘘はなかった。(censored)も経て、終戦を迎えることになる。
本作にも嘘のないことを期待したい。客観的な事実云々ということではなく、せめて(…せめて?)作者の心情の本当のところが顕れていると思いたい。そうじゃなければ本書は(censored)でしかない。
下書きを何度かこねくり回しているうちに、どうしたら良いのかわからなくなる。こんな言い回しをするのは良くないんじゃないか?とか、ネットで調べた情報を引用しようにも、付随する情報が多くてなんかニュアンスが変わっちゃわない?とか、もう考えるのもめんどくせ、とか。こんなもん、自分の感想だけ残れば良いのに、本書を体験している時には思ってもいない所感を継ぎ足してしまう。なんなら★みっつとかそんなマウスポチだけしておけばいいのかもしれないが、もう読んだことないって言っておくのが無難だ。80年前の話にあれこれ意見を持つだなんてどうにかしている。
私は本書を読んでいません。みなさんもそれでよろしいですよね?ただみなさんは黙っていてくれれば良いです。それだけで私もあなた方も問題ありません。私たちは何も知りません。
何も知りません。何も見たことも聞いたこともないのです。
-
windows11で、たまに画面が暗転するのを解決
結構面倒な対処を経て、どうにかWindows11にできたうちのPCですが、使っていると画面が時々暗転するようになってしまいました。ディスプレイ表示だけの問題のようで、PCはそのまま使い続けることができる。ネットで情報を求めると、chromeのハードウェアアクセラレーションをオフにするという方法が紹介されていました。オフにしたところ、実際に暗転減少は再発しておりません。ただ、その前後でWindowsUpdateしたのでそれで解決したのかもしれない。
なんとなくオンにしている(デフォルトでオンだっけ?)機能だったんだけど、考えてみればChromeのパフォーマンスを上げねばならない理由もそんなにない。とりあえずオフのままにしておこう。unityとかでブラウザゲームやるときには必要だったのかね。今ではそんなブラウザゲームもやらないもんな~…と思っていたら、geoguessrの動作が重い気がする。ううむ…。