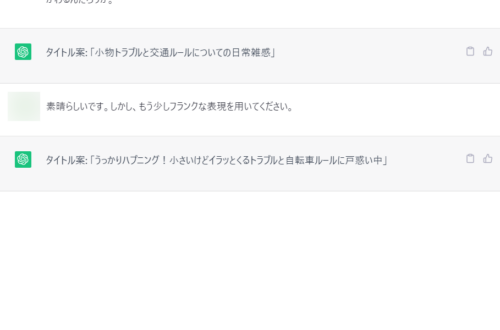-
めし短観
トリュフの香りのする芳醇なポテチなるものを食ったけど、なによりしょっぱすぎて、美味しいとは思えなかった。自分は本物のトリュフって食べたことないと思う。キャビアはあるけど、フォアグラはねえな。「三大珍味」なんて今時も言うのだろうか。わからない。
デパ地下で食材を買ったことが、多分ない。ああいうところには、本当に高級な食材が置いてあるんだそうだ。へー。とはいえ、赴くのはクッソだるいので、いつものスーパーでざっくりグラム単位で見比べ、一番高い牛肉を買ってみた。焼き肉用の希少部位っぽいものだったが焼き肉も行かないし名前になじみがない。フライパンで適当にじゅわじゅわ。塩レモン味で食う。美味しかったことは間違いないが、肉っぽさが薄く、妙な甘さを感じて不思議というか…。たぶん調理方法にもよるからあまり気にしないことにしよう。高い肉is美味い。
カップヌードルにPROなる商品があったので食ってみた。高たんぱく低糖質だそうな。味は、いつの間にか見かけなくなったlightと同じような味だった。…いや、これは同じ商品なのでは?すぐに無くなりそうな予感しますねこれは。一方、カレーメシなる商品にも手を出してみたが、これはなかなかに美味でありました。これは書いたっけ。
本年の正月に非常用バッグのメンテしなかったようで、賞味期限が今年一月のチョコレート、今年三月のカロリーメイトなど出てきた。危機管理とは。以前は無慈悲に廃棄したが、今回は頂いてみることにした。チョコレートはクッソ不味かったので半分廃棄。半分は慈悲。カロリーメイトは普通だった。食後の体調にも問題は無し。やはりフルーツ味が好きだ。一般的なジュースやゼリーの甘い感じのフルーツではなく、はっさくの皮ごと食っているような、少し苦みのある風味がたまらない。グレープフルーツの風味かね、あれは。
タケノコの水煮を買って、細切りにして青椒肉絲…とするところ、包丁でちまちまやるのが面倒になり、メンマぐらいのサイズ感で炒めて食った。このサイズなら肉いらないのでは?肉を切るのもめんどうくせえと思い、ピーマンとタケノコのみ。味付けに塩。春っぽくてとても良い。そういえば今年はふきのとうの天ぷらやらなかった。特段好きなわけでもないんだけどな、春に春っぽいものを頂くということが、摂理を重んじ以て涅槃に雨を呼び冷たく清めていると覚えて大変に誇らしい気持ちになる。蓮の香りのする芳醇なピザ(糖質カロリーゼロ)が春の名産品になったら、浄土も海へ沈めて見せやう。
-
ざっき
GO TO イートとかトラベルとか、結局なんなのだろう?自分の周りでは実際に使ったという事例を直接は知らないので、お国が先導してなにか割引キャンペーンをやりました、程度の認識でいる。結局は将来の自分たちが払う税金に跳ね返るだけだと思う。将来への備えとして、使わずに過ごすこととしたい。しかし、観光業って我が国でそんなメインのビジネスなんだろうか…。
聖火リレーが始まった。本気でオリンピックやるの?開催する理由がどうせビジネス事情だなんてことは、みんなわかってると思う。中止にするより経済的にはマシみたいな考えなんだろうか。もう何もかも破れかぶれみたいな印象しかないんだが、どうなることか。
天井の照明の電球が切れたんで買ってきた。あまり考えずに口径が合うかだけで買ったので、色も明るさもだいぶ違う照明になった。賃貸住まいであるからして、退去するときに、元の色に戻せなんて言われねえだろうな。
ミャンマーは内戦でも始まったのだろうか。伝わってくるニュースが苛烈だ。ミャンマー…子供の頃はビルマって名前だった。ビルマの竪琴は観たことない。(Amazonプライムで観れるの気づいたンゴ)北部は治安がやばい。そのぐらいの知識しかない。時代が時代なので、報道機関の情報などを待たずとも、現地に住んでいる日本人から動画が届くこともある。市民に発砲して犠牲者が、なんてニュースが流れてくるような状況だからだろうか、ここ数日のものはさすがに見当たらない。他のニュースソースによれば、プラスチックの破片で鏃を作り、スリングショットで何かを投擲して、発泡スチロールの防弾チョッキで立ち向かっているんだそうな。市民もこうして死ぬ覚悟で戦っているのであれば、簡単には収まらない筈で…。
最近また、肩がこる。人間、なにか怪我をしたり体を痛めると、他の人にもそういうことがないか、聞いてみるもんだ。みんな、こるって。以上。
桜玉吉の新刊が出たので読んでみた。山の中で暮らすの大変なんだな、と。あんなところに住むと、虫や植物と戦うことになるようだ。この暮らしが快適だ、というエピソードがあまり出てこないんだけど、当人はそれなりに自然とのじゃれあいを楽しんいると思う。近場の温泉には楽しそうに通っておられるので、よかったよかった。こういう…田舎というか過疎地の暮らしを楽しそうだとは思うけど、実際に始めてみるとどうなるだろうか…。
暖かくなってきた。つーと梅雨に近づく。風呂に設置したツッパリ棒を変えて取り外しが簡単になるものにした。今までのは一度外れるともう一回つけるのに大変難儀する。捨ててしまうのだけど、この、細長いものは粗大ごみになるというルールどうにかならんか?大きさが小さくなれば燃えないゴミだって。こんな頑丈なもんを折らんといかん。プチプチで丁寧にくるんで、全体重でどすーんとやれば大丈夫だろか。
-
いろいろ読んだり観たり。
「HUNTERxHUNTER」を読んだ。蟻の王様の続きぐらいからは、単行本も買ってなかったので読んだことがなく、Amazonで最新版まで一気にお買い上げして読んだ。なんというかこう…よくもこんなにいろいろ考えるものだと感心してしまう。念能力がどうのこうの、人物関係がどうの。こういう情報を整理できるというのはクリエイターの要件なのかもなあ。
オードリー・タン氏が作中のキャラクターである「センリツ」に見えてしょうがない。
で、今回拝読した結果、最新刊に追いついたんだけども、数年前に読んだことのある内容でびっくりしてしまった。おそらくはジャンプの立ち読みでもしたんじゃないかと思う。「お~連載してるな~」なんて。調べたら最後の連載は2018年の終わりのほうだったということで。このまま休載を繰り返し、最後は「バスタード」の二の舞になってしまうんだろうか。
「タクシードライバー」を観た。これといって面白くは無かった。
「ゴルゴ13」を読んだ。なんとAmazonプライム枠で、1~3巻まで読めたので堪能。ところでこの初期ゴルゴはところどころで違和感を覚える。自分の知っているゴルゴとは振る舞いが異なる。例えば、車に率先して乗り込む。自分の知るゴルゴは、先に乗れと促して自分からは進んで乗らない。他にも狂言回し的なセリフを並べたりする…。いつから自分の知るようなゴルゴになったんだろうか、という興味はあるけど、さすがに全部読んでもいられない。1巻のエピソードには制作年が1969年と記されている。現代に至るまでに、作中では新型軍事テクノロジーがほどほどの調整をされて登場したり、作品部隊がアップデートされてゴルゴがインターネットメールを受信したり、その他、時事ネタが登場したりもする。それでも、ゴルゴ自身はスナイパーライフルをメインに仕事をする様子は変わらない。(宇宙で弓を射たりもしたけど…)
国家間のこういうウラのもめごとは実在するだろうし、今後もなくなる見込みはなさそうだ、というあたりが、こんにちまで作品に緊張感を与え、その寿命を延ばしているような気がする。もちろん、キャラクターの魅力があっての話。軍事ドローン飛ばして「任務完了!」では作品が成り立たん。でも、軍事の世界にまったく触れられないというのも、時代劇じゃないんだからさあ…となってしまうように思う。自分は実際に見たことはないけど、ドラえもんの世界にもスマホが登場するように設定変更されたらしい。ゴルゴ13の世界は、そんな唐突に変化するでもなく、じんわりと世界の変化に沿っている気がする。本人以外については、自然に時代に追いつくことに成功しているほうなんじゃないか?デューク東郷はどうするんだろう。こち亀方式で、年齢は気にしないのが平和なのかね。最新刊をチェックしたら200巻が間もなく発売。買うか。
「dancyu」を読んだ。シンプルパスタだって。内容は普通のパスタ料理が並んでいるだけだった。レトルトのソースや缶詰の中身を茹でたパスタにかけておしまい、というのをシンプルというのだ痴れ者。出なおしてこい。「こだわりパスタ」でも同じようなものが記事に並びそうで恐ろしいわ~。
-
ゆらゆら帝都
地震はいつか絶対来るなんてことは承知の助でありんす。地球の仕組みに依るものだから、絶対になくならない。
「そろそろ」危ないなんて話を何年も伝え続けてもさほど価値のある情報といえないと思う。俺は前から同じようなこと言うてるな。毎日地震予報しなさい。んで、先日の地震の際、自宅にいたので揺れが収まった後、思いついてPC机の下にもぐってみた。避難訓練であります。体の収まりを確認してみると、自分の体型でも全身が天板でガードされる格好になった。ただ、土下座というかハイハイの姿勢にならざるを得ない。上下ひっくり返って、つまり、仰向け立膝の姿勢になると、踵あたりから天板からはみ出ているようだ。まあ本気の非常時にそんな体制で潜り込むわけはないのだが…。横向きでも事情は同じようなもんだった。建物崩落して閉じ込められ、長時間サバイバルを強いられるような事態になれば、姿勢を変えることができるのは大変に生存確率あがるのでは…うーんどうだろうか。
机の下には、飲料水と缶詰と、例の水で戻せるご飯がストックしてある。LEDの懐中電灯もある。あとは靴と靴下も置いておけば良いのかもしれないが、スペースも無限にあるわけではない。建物が崩落!机の下で一命を取り留めたが出るに出られない!というときに、五体満足なら三日は生存可能な量がある。だけどね、この建物ごと崩れる地震が東京にやってきて、三日で自分のもとに救助が来るなんて…うーんどうだろうか。来ないよな普通に考えて。
兎に角、実際にもぐってみて、もうちょっと「その時」にも使えそうな備蓄を机の下に移動しておくか、などと思った。不安に駆られたと言えばその通りだが、実際に助かる可能性にかける余地があるのではないか?と希望を見出したともいえる。まーーーそんな怖ければーーーー東京離れろってえ話ですがーーー。
地震台風テポドン火山自治体の財政治安隣人(censored)、いろんなリスクを考えて国内で一番安全っぽいのはどこだろうか、すぐ結論でるんじゃないかと思った。岡山島根鳥取の近辺だろうって。でも、人生を捨てて放蕩しようってんじゃない。生活をするんだ。将来を見据えてではなく、明日引っ越しますぐらいの勢いで移住できるところ。インターネットが安定していれば趣味と暮らしはOK(と言い切る覚悟がこの20年定まらない)仕事は…うーん、どうだろうか。大体さあ、武蔵小杉の失敗例にあるように、急激に人気になるエリアはインフラや行政が追いつかないことがある。充実を待てば安くは住めない…うーんどうだろうか。
さてさて。こういった検討を、どこまで実践したらよいのか、いまだに全くわからない。自分が人生で身に着けた知識が、体験が、こんなことも判断できない。決断して実行できない大人が一番イタイ。情報を集めるだけなら、みんな小一時間で同じ情報レベルに到達できる世の中。情報量をどう評価するのか。〇〇という判断をするに足りるのかどうか。
…などと書いていたら、下記のような資料のニュースが届きました。
https://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/
地震の発生隔離を色分けして日本地図にプロットしているんだけど、分けパターンに違和感を覚えるというか…なんだろうこれは。色分けの閾値がパーセント区切りで、0-0.1-3-6-26-100となっている。技術的に意味のある区切り方なんだろうか。例えば、俺の住んでる街は6%起こるらしいぞ!というのを、どう評価するのか、結局わからない。300年とか500年とか時間のスパンだったら自分に意味がないと判断できるけど、技術的に正確性は落ちそうだよね。実際のところ、関東一円は全部26-100%のエリアなんで深く考えることもない。震度6ぐらいなら絶対起きると思っておけば良いようだ。ということは、それでは済まない規模も起こりえるんだろう。
心配だけが募る。地震に恋でもしてるのか俺は。どれだけ心配しても極論すれば、その瞬間何処にいて何をしているのか、そういう運の要素を否定できない。だから、運が良いときにその瞬間が来ると仮定して、その運を逃すものかと考えれば…あれこれ自宅で備えるのは無駄にならんと信じたい。逆に地下鉄に乗っているときに発生、とかだったらもう知らない。ばーかばーか。
でも、スマホのモバイルバッテリーを持たずに電車に乗って出かけたことは、あの地震以降一度も無いんじゃないかな…。